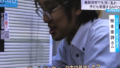みなさんこんにちは。
スタッフの大倉です。
中学生の相談でGWが開け毎年多いのが、学校に行きたくないと言い始めたという相談です。
・不登校までいかなくとも、ほっとくと長期化しそう。
・中学夏休み明けなどが危なそう
など不安に思っている方は是非参考にしてください。
GW明けから登校を渋る子が急増?夏休み前の“心の危険信号”
GW明けの登校しぶりは、夏休みの引きこもりリスクの“前兆”かもしれません。
5月は進級後の疲れが出やすく、特に中学生は思春期の不安定さも加わって精神的に揺れやすい時期。ここで登校しぶりが始まると、夏休みをきっかけにそのまま引きこもってしまうケースも。
「朝になるとお腹が痛くなる」「夜ふかしが増える」「外出を嫌がる」などが見られたら注意信号です。
この段階で家庭ができることに取り組めば、長期の引きこもりを予防できます。

なぜ中学生は夏休みに引きこもりやすくなるのか?
夏休みは、中学生にとってリズムが崩れやすく引きこもりのリスクが高まる時期です。
学校がないことで生活のメリハリがなくなり、人間関係や学習のストレスを“回避”できてしまうことで、社会との接点が失われていきます。
また、最近の日本の暑さで毎日冷房にあたっているところから、外に出るために普段より体力を使ってしまうという季節的な要因もあります。
ゲームやスマホだけの世界に没頭し、人と関わるのが億劫になったまま夏が終わり、気力も体力も尽きて、9月以降の登校が困難になる生徒は少なくありません。
だからこそ、“今”の関わりがその後の生活を大きく左右します。
引きこもり予備軍のサインを見逃さないために
小さな異変を見逃さないことが、夏休みの引きこもりを防ぐ第一歩です。
完全に部屋にこもる前に、必ず予兆があります。
「昼夜逆転」「外に出たがらない」「家族と話さない」「感情の起伏が激しい」などがそれにあたります。
早めに気づけば、引きこもりを“未然に”防ぐことができます。
特に睡眠時間は重要で、夏休みは、好きなだけスマホを使える場合が多く、睡眠時間が不足しがちです。
厚生労働省でも中高生は8~10時間の睡眠を推奨していて、規則正しい生活が、十分な睡眠時間の確保につながります。
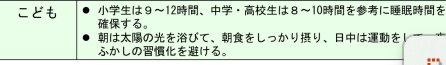
ちょっとした生活習慣の工夫が引きこもりを防ぐ
生活習慣を“完全に戻す”必要はありませんが、乱れきらない工夫が効果的です。
昼夜逆転や極端なスマホ依存は引きこもりリスクを高めます。
例えば:①起床時間を8〜10時の間で統一する/②週1回の親子外出を提案する/③“朝ごはんを一緒に食べるだけ”の習慣をつくる
小さなルールが“社会との接点”を残すカギになります。
まとめ|夏休みの過ごし方が“9月不登校”を防ぐカギに
今の過ごし方次第で、秋からの生活が大きく変わります。
中学生は自分で環境を変えるのが難しいからこそ、家庭の関わりが重要です。
GW明けの登校しぶりから夏休みを経て、そのまま引きこもるケースを多く見てきました。
“うちの子は大丈夫”と思わず、今から声かけ・生活習慣・専門家の活用など、小さなアクションを始めましょう。
相談したいという方は、是非ご相談ください!
以下リンクよりご相談できます!
https://kousotsu.jp/raishomendan/