家庭内暴力なんて・・ なぜ、うちの子が……
不登校になった我が子が、家の中で暴力をふるう。 今まで優しかったあの子が、怒鳴り散らしたり、物を投げたり、時には親に手をあげてくる。
そのたびに、親は大きなショックを受け、戸惑い、深く傷つきます。
「どうしてこんなことになってしまったんだろう?」 「誰にも相談できない……」
この状況は、親にとって想像を絶するつらさです。 しかし、一人で抱え込む必要はありません。
このブログでは、不登校の子どもが家庭内で暴力をふるってしまう背景から、具体的な対応策、そして子どもだけでなく親自身がどう行動すべきかまで、専門家や実際に経験された方の声も交えながら、詳しく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「もしかしたら、この状況を変えられるかもしれない」と、少しでも希望を感じていただけたら幸いです。
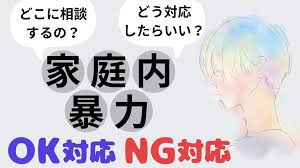
なぜ不登校の子どもが家庭内で暴力をふるうのか?
「不登校」「引きこもり」と「家庭内暴力」という二つの問題は、実は密接に関係しています。
多くの場合、暴力は子どもが抱える苦しさやSOSのサインです。
引きこもりと感情コントロールの関係
不登校になり、家に引きこもる生活が続くと、子どもは社会との接点を失います。 学校という他者との関わりの中で、人は自然と感情を調整する方法を学びますが、その機会が失われてしまうのです。
例えば、
- 友達との会話で自分の感情を言葉にする
- スポーツやゲームで負けて悔しい気持ちを乗り越える
- 先生に叱られて、自分の行動を反省する
こうした経験がなくなることで、感情の起伏をコントロールする術がわからなくなり、感情の揺れがそのまま暴力という形で表れてしまうことがあります。
「暴力」というSOSにどう気づくか?
子どもの暴力は、単なる「わがまま」や「反抗期」ではありません。 多くの場合、それは「苦しい」「助けてほしい」という、言葉にできない心の叫びです。
もし、お子さんが以下のような状態であれば、それは「SOS」かもしれません。
- 学校に行けないことへの強い焦りや罪悪感を抱えている
- 自分の不甲斐なさや将来への不安で、どうしようもない気持ちになっている
- 親がかけてくれる言葉を、「自分のことをわかってくれない」と誤解し、孤立感を深めている
- 以前はできていたコミュニケーションがうまくとれなくなり、イライラが募っている
こうした感情が積み重なり、限界を超えたとき、子どもは「暴力」という最もわかりやすい形で、自分の苦しさを表現しようとするのです。 このSOSに気づき、根本的な原因に向き合うことが、解決への第一歩となります。
母子分離から起きる悪循環とは?
不登校の子どもは、母親に対して強い依存を示す傾向があります。 母親もまた、子どもを心配するあまり、必要以上に干渉、対応してしまうことがあります。
この「密着した母子関係」は、一見すると支え合っているように見えますが、実は悪循環を生み出す温床となりかねません。
- 子どもの依存が高まる: 母親との関係に安心を求めるあまり、自立する機会を失う。
- 母親の疲弊: 常に子どもの感情に振り回され、精神的・肉体的に疲弊していく。
- 子どものフラストレーション: 母親の過度な干渉が、子どもにとっては「自由がない」「自分のことをわかってもらえない」と感じ、フラストレーションがたまる。
- 暴力の発生: 溜まったフラストレーションが、最も身近な存在である母親への暴力として噴出する。
この悪循環を断ち切るために、第三者的な存在の介入が有効です。
家庭内暴力の解決法を実例から学ぶ
「父親が介入すると落ち着いた」実例から学ぶ
実際に多くのご家庭で、母親への暴力が絶えなかった子どもが、父親が関わり始めてから暴力が減り、落ち着きを取り戻したというケースが報告されています。
これは、
- 力や存在感の違い: 子どもは、母親とは違う「父親」という存在を意識し、感情のままに暴力をふるうことをためらうようになる。
- 新たな視点の提供: 父親が関わることで、子どもは母親とは違う価値観や考え方に触れる機会を得られる。
- 母親の負担軽減: 母親が一人で抱え込んでいたプレッシャーが軽減され、心に余裕が生まれる。
父親の関わりは、子どもと母親、双方にとっての「変化」をもたらす力を持っています。
ただし、以下のような例に当てはまる場合は、第三者の力を借りたり、相談をすることも検討してください。
例 ・父親が介入すると余計に暴れ始めてしまう。
・父親がそもそも積極体に関わってくれないなど・・・。
家庭内暴力に対する外部の公共の相談機関
不登校かつ、家庭内暴力がある場合、以下のような公共の相談機関が選択肢としてあります。
【子ども家庭庁 子どもの虐待の相談窓口】
https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/
→子どもの家庭内暴力の相談もできます。
【厚生労働省 まもろうよこころ】
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/?yclid=YSS.EAIaIQobChMI_MeXsdvyjgMVQlwPAh1vcA_MEAAYBCAAEgLrr_D_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=&sa_t=1754364064045&sa_ra=AA
→広く一般的な相談を受け付けています。
【児童相談所全国共通ダイヤル「189」】
24時間365日対応
お近くの児童相談所につながります。
虐待だけでなく、育児や子どもの発達に関する様々な相談に応じてくれます。
【警察庁「#9110」】
お住まいの地域の警察相談専用電話につながります。
緊急性が高くないものの、「どうしたらいいか分からない」という悩みを聞いてもらえます。
家庭内暴力が落ち着いた後に必要な3つのステップ
家庭内暴力が外部の力を借りて収まったとしても、それはあくまで第一歩です。 子どもが再び社会に踏み出せるよう、継続的な支援と「家庭の関わり方」の見直しが大切になります。
生活リズムを整える
不登校生活が長く続くと、昼夜逆転の生活になりがちです。 この乱れた生活リズムを立て直すことは、心身の安定に欠かせません。
- 家族で決めたルール(夜は12時までに寝る、朝は9時には起きるなど)を徹底する
- 日中に外出する機会をつくる(親子で散歩に出かけるなど)
また、民間の支援機関の中には、寮や合宿形式で生活リズムを整えるプログラムを提供しているところもあります。また、高卒支援会では、保護者だけではなかなか進まない次の一歩を訪問支援。
アウトリーチとしてサポートすることを行っています。
自信を育てる学び直し
不登校の背景には、学業の遅れや自信の喪失が隠れていることがあります。 暴力をふるう原因の一つが、この「自信のなさ」であることも少なくありません。
- フリースクールや通信制高校を利用し、自分のペースで学び直す
- 得意なことや興味のある分野(プログラミング、イラスト、音楽など)を伸ばす機会をつくる
- 親が「勉強しなさい」と口うるさく言うのではなく、「一緒に調べてみようか」「面白いね」と、子どもの興味を尊重する
「勉強」だけにとらわれず、子どもが「できること」を増やし、成功体験を積ませて自信を回復させることが重要です。
高卒支援会のフリースクール、通信制高校のページはこちら
社会との接点をつくるアルバイト・インターン
学業の遅れを取り戻し、少しずつ自信がついてきたら、社会との小さな接点をつくっていくことを検討してみましょう。
- 短期のアルバイトや単発の仕事
- 興味のある分野のインターンシップ
- ボランティア活動
こうした経験は、「自分は社会の役に立てる」という自己肯定感を育む貴重な機会になります。 最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、「スモールステップ」で挑戦できるものから始めてみましょう。
高卒支援会では、在校生に訪問支援を手伝ってもらったり、事務のお手伝いなど自分の自身の解決につながる活動が可能です。
今の行動が未来を変える第一歩になる
「こんな状態がいつまで続くんだろう……」 そう絶望的な気持ちになる日もあるかもしれません。
しかし、「第三者に相談してみよう」「警察・児童相談所に電話してみよう」 そう決心した、今のあなたの行動が、きっと未来を変える第一歩になります。
どうか、一人で抱え込まず、外部の力を借りてみてください。 あなたと、お子さんの明るい未来のために、今できることを少しずつ始めていきましょう。
何かお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。
ご相談はこちら↓
https://kousotsu.jp/raishomendan/


